皆さん、鶴と亀が縁起が良い生き物であることご存じでしょうか?鶴は千年、亀は万年というフレーズを聞いたことがない人はいないと思います。それくらい日本で縁起の良い生き物と言ったら鶴と亀が真っ先に挙げられます。では一体なぜ鶴と亀は縁起が良いとされているのでしょうか。また具体的に鶴と亀はどんなことを象徴しているのでしょうか。また日本以外の国では鶴と亀はどんな風に捉えられているのでしょうか。今回はそんな縁起が良いと言われている鶴と亀について深ぼっていきます。
鶴と亀が縁起が良い理由

日本で鶴と亀が縁起の良い生き物とされているのは、古くから彼らが長寿を象徴する生き物であるという考えがあるためです。この考え方は日本独自のものではなく、実は中国からの影響を受けたものです。中国の前漢時代に書かれた思想書には、鶴は千年、亀は万年生きるという言い伝えが記されており、この思想が日本にも伝わったのです。
室町時代以降、日本ではこの考えを取り入れ、特に能の舞台ではこの長寿の象徴が顕著に表されます。「鶴亀」という演目は、中国の皇帝の長寿を祝うために、鶴と亀の冠を着けた舞人が舞うという内容です。この能の演目からも鶴と亀が長寿で縁起が良いとされる思想が中国から伝わったことが伺えます。
このように、日本で鶴と亀が縁起の良い象徴とされているのは、その長寿を象徴する性質と、それが中国からの文化的影響を受けていることによります。この伝統は、歴史を通じて日本の文化や芸術に深く根ざしています。
鶴は夫婦仲や健康長寿の象徴も世界では不吉の象徴

日本における鶴は、長寿や縁起の良さの象徴として知られるだけでなく、夫婦の良好な関係や絆を象徴する「夫婦鶴(めおとづる)」としても親しまれています。夫婦鶴は、夫婦の仲の良さや生涯連れ添う姿を表し、結婚式の祝儀袋や席札などに用いられることが多いです。特に、和の厳粛な雰囲気がある神社での神前式や、寺などの仏閣で行われる仏前式などでは、この夫婦鶴が好まれます。
また、鶴は「千羽鶴」としても有名で、これは折り紙で作られた鶴のことを指します。室町時代には長寿の願いを込めて折り鶴が作られ始め、江戸時代には病気の快癒や長寿を願う千羽鶴が作られるようになりました。現代では、平和のシンボルとしても千羽鶴が用いられています。
一方で、鶴に対する見方は国や文化によって大きく異なります。日本で鶴が縁起が良い動物として尊重されているのとは対照的に、北欧では「死を運ぶ鳥」として不吉の象徴とされたり、ケルト神話では殺戮を好む神エススと共に描かれるなど、不吉な鳥としての象徴となっています。
このように、同じ鶴であっても、文化や地域によってその意味や象徴するものが大きく異なり、それぞれの文化の中での鶴の位置づけや解釈の違いが興味深い点です。日本では鶴がもたらす幸福や願い事を象徴する一方で、他の地域では全く異なる意味を持つことから、文化の多様性や解釈の幅がうかがえます。
亀は長寿、金運を象徴し世界を支える生き物という信仰

亀は長寿や繁栄の象徴として、世界中で縁起の良い生き物とみなされています。古代中国では、仙人が住むとされる逢莱山の使いとして親しまれ、日本の伝説では浦島太郎の物語の中で竜宮城の使いとして知られています。このように、亀は古くから縁起物として大切にされてきました。
「亀は万年」という言葉に象徴されるように、亀はその長寿によって特に重宝されています。亀の甲羅に見られる六角形は吉兆を表すとされ、その硬さは不動の力を象徴していると考えられています。また、亀は金運を招く縁起物としても扱われることがあり、「ゼニガメ」や「イシガメ」の名は、その甲羅が江戸時代の通貨に似ていることから来ています。
亀の寿命は人間に比べて長く、種類によっては平均で30~50年生きるとされ、中には150年以上生きた記録も残っています。江戸時代の日本人の平均寿命を考えると、「亀は万年」という表現が生まれた背景にも頷けます。特に「みのがめ」と呼ばれる亀は、背中に苔が生えたような見た目から、さらに長寿を象徴するものとされています。
世界的にも、亀は縁起の良い生き物として広く認識されています。古代インドでは世界を支える存在としてウミガメが描かれ、南洋諸島やネイティブ・アメリカンの伝説では亀が山を支えるという信仰が見られます。これらの例からも、亀がもたらす好ましい象徴は国境を越えて共有されていることがわかります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は鶴と亀がなぜ縁起が良い生き物として信じられているのか見てきました。鶴も亀も長寿であるという思想が中国から伝わったことが背景でした。鶴はそれ以外にも夫婦仲や健康長寿の象徴として、亀は金運の象徴として見られていますが、日本以外では鶴は不吉の象徴で亀は世界を支えている不動の存在というように受け取られ方が異なっていました。このように同じ動物でも捉えられ方が国によって異なるのは興味深いですね。
本サイトでは鶴と亀以外にも様々な日本の面白い文化や歴史を紹介しています。興味ある方はぜひ他の記事も読んでいただけると嬉しいです!






































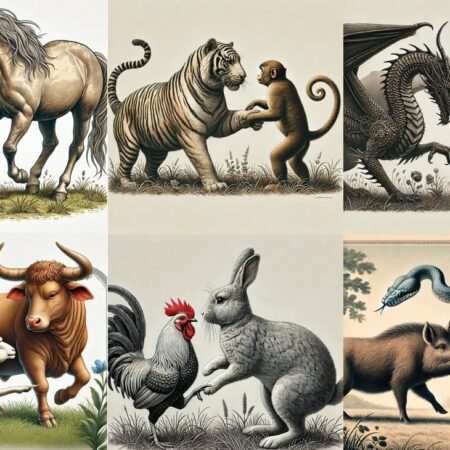



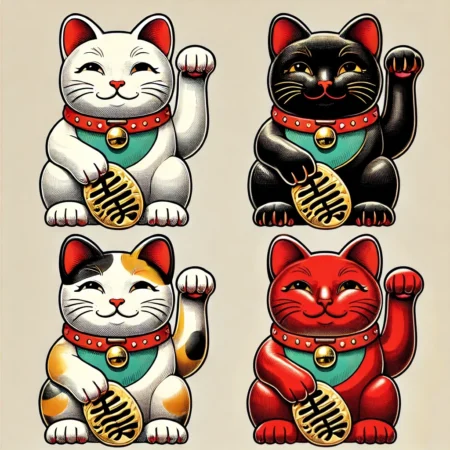
コメント